1.親の顔色をうかがう自分へ、そっと気づくために
子どものころ、わたしたちは誰かに教わったわけでもないのに、いつの間にか「親の気持ちを先回りして考える」ということを覚えていきました。
言葉には出さなくても、「怒られないように」「嫌われないように」そうやって、何度も何度も、心の中で先読みを繰り返していたのです。
それは、「過保護」や「過干渉」という言葉だけではとても説明しきれない、静かで見えにくい経験です。
誰かが「うちはそんなにひどくないよ」と言ったとしても、その中で生きてきたあなたの“感じたこと”は、確かにそこにあったものです。
だからこそ、「自分はそれに当てはまらないかもしれない」と迷いながらも、どこか心が苦しくなるのは自然なことです。
わたしたちは、自分の心の動きに「これは正しいことなのか」「間違っているのか」という判断をすぐに下そうとしてしまいます。
でも本当は、「つらかった」という感覚に正しいも間違いもありません。
それを感じた自分がいる。
そのことを、まず静かに受けとめてあげることが、とても大切なのだと思います。
では、「なぜ先読みをしてしまうのか」「それがどうして心の苦しさにつながるのか」ということを、解説していきたいと思います。
もし、あなたが「わかってもらえない」と感じたことがあるなら、それは、あなたが間違っているからではありません。
見えにくいものに、目を向けること。
声にならない思いに、静かに耳を傾けること。
そうやって、自分を少しずつ大切にすることが回復への小さな一歩になるのだと思っています。
・ある日の夕方、リビングで
夕方、テレビの音がぼんやりと流れるリビングで、あなたは学校から帰ってきたランドセルを静かに床に置きます。
「ただいま」と声をかけると、キッチンで料理をしている親が、ちらりとこちらを見る。
その一瞬の表情を見て、今日の家の“空気”を読み取ろうとする。
声のトーン、包丁のリズム、返事の仕方――
何気ない動作のひとつひとつに、「怒ってないかな」「機嫌はどうかな」と心のアンテナを張り巡らせる。
誰に教わったわけでもない。
でも、いつの間にかそれが習慣になっていた。
何も言われていないのに、「手伝わなきゃ」と思って動いてみたり、逆に、「今は話しかけない方がいい」とそっと自分を引っ込めたり。
ほんとうは、「今日ね、学校でちょっと嫌なことがあって…」と話したかったのに、それは飲み込んでしまう。
“親の気持ちに合わせること”が最優先になると、自分の気持ちは、いつもあと回しになってしまう。
でも――
そんなふうに一日を過ごして、夜になってベッドに入るころ、ふと、ぽっかり空いたような気持ちになることがある。
「自分はちゃんと、生きてるのかな」
「わたしのこと、見てくれてるのかな」
そんなふうに感じるときがあったとしても、それは弱さではなく、ほんとうの自分が、静かに何かを伝えようとしているサインかもしれません。
「好きなこと」を言えなかった日
夕方、テレビの音がぼんやりと流れるリビングで、あなたは学校から帰ってきたランドセルを静かに床に置きます。
「ただいま」と声をかけると、キッチンで料理をしている親が、ちらりとこちらを振り返る。
その一瞬の表情を見て、今日の家の“空気”を読み取ろうとする。
声のトーン、包丁のリズム、返事の仕方――
何気ない動作のひとつひとつに、「怒ってないかな」「機嫌はどうかな」と心のアンテナを張り巡らせる。
誰に教わったわけでもない。
でも、いつの間にかそれが習慣になっていた。
何も言われていないのに、「手伝わなきゃ」と思って動いてみたり、逆に、「今は話しかけない方がいい」とそっと自分を引っ込めたり。
ほんとうは、「今日ね、学校でちょっと嫌なことがあって…」と話したかったのに、それを飲み込んでしまう。
“親の気持ちに合わせる”が最優先にして、あなたの気持ちは、いつもあと回しに。
でも――
そんなふうに一日を過ごして、夜になってベッドに入るころ、ふと、ぽっかり空いたような気持ちになることも。
「自分はちゃんと、生きてるのかな」
「わたしのこと、見てくれてるのかな」
そんなふうに感じるときがあっても、それは弱さではないのです。ほんとうのあなたが、あなた自身へ静かに何かを伝えようとしているサインかもしれません。
家に帰る時間を選ぶようになった日
学校が終わると、友達と少し遊んで帰りたかった。
でも、「遅く帰ったら、きっと何か言われる」そう思って、急いで家に帰った。
家に入る前、玄関の前で一度、深呼吸する。
「ただいま」と言ったときの親の反応が、その日のすべてを決めるような気がしていた。
もし無言だったら、怒ってるかもしれない。
ちょっと冷たい口調だったら、何か不満があるのかもしれない。
その“かもしれない”の不安が、毎日の行動を決めていく。
安心して帰れるはずの「家」が、いつの間にか「空気を読む場所」になっていた。
「大丈夫」としか言えなかった夜
学校で友達とうまくいかなくて、帰り道に涙がこぼれそうになった日。
本当は、誰かに話を聞いてほしかった。
ただ、そばにいてほしかった。
でも、家に帰って顔を合わせると、「何かあったの?」と聞かれても、とっさに出た言葉は「大丈夫」。
心はぜんぜん大丈夫じゃないのに、“心配をかけちゃダメ”という思いが先に出てしまう。
そうして、誰にも気づかれずに泣きたい夜をひとりで過ごすことが、少しずつ当たり前になっていく。
2.母親の持つ秘密を感じ取ってしまった子ども
気づいたときには、子どもたちの心は、「おびえ」と「愛しさ」が入り混じったまま、
母親というたったひとつの世界の中に、深く、深く入り込んでいました。
その関係の中で、母の不安や痛みに気づいた子どもは、それを「感じ取ること」自体が、自分の役目だと感じるようになります。
そうして、「母を守らなければならない」という思いが誰にも言えない“秘密”として、心の奥にずっとしまわれていくのです。

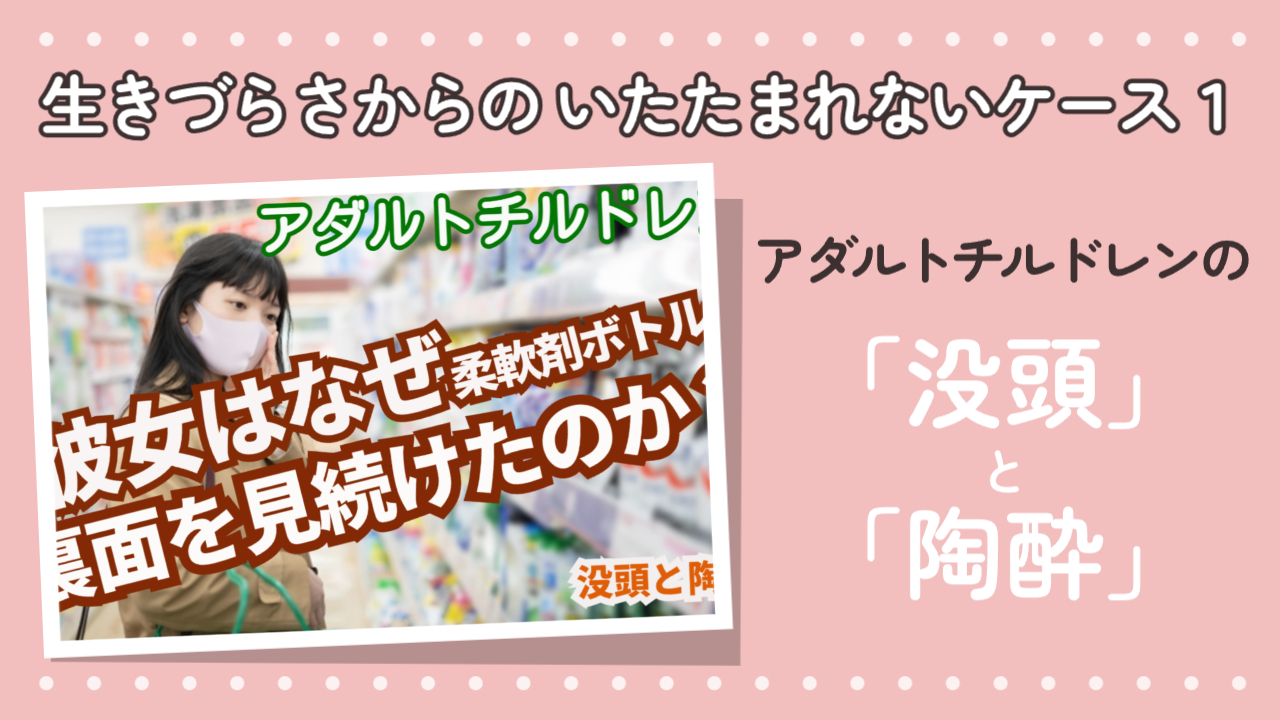

コメント