1.否定される感覚のその先に──「母親に執着していく子どもたち」
否定される体験が積み重なるほどに、子どもは自分の感情や考えを信じることができなくなっていきます。
「私はこう思う」「こうしたい」といった自然な気持ちよりも、「お母さんは今、どう思っているのか」「どの言葉なら嫌われないか」──
そんな“先読み”が、日常の大半を占めていきます。
心のバランスを取るために、子どもは無意識のうちに、母親の表情、声色、沈黙、そのすべてに過敏になっていきます。
最初はただ、否定されるのが怖かっただけかもしれません。
でもそのうちに、「母親の望む自分でいないと存在できない」──
そんな思い込みが深く根づいてしまうのです。
この頃になると、子どもにとって母親は、「怖いけれど、離れられない」存在になります。
少しでも遠ざかろうとすると不安になり、逆に、そばにいればいるほど緊張し、苦しくなる。
その矛盾した関係の中で、子どもはどんどん「自由な意思」や「感情の選択肢」を失っていきます。
そして、気づかないうちに、母親の価値観や感情を自分の中に取り込みます。
まるで、自分と母親の境界線が曖昧になっていくように──。
ここで起こっているのは、母親との“癒着”だけではありません。
同時に、「母親の求める役割」を無意識に演じ続けることで、子どもは母親の“支配”の中に入り込んでいくのです。
たとえば──
母親が落ち込んでいると、自分のせいだと思ってしまう。
「あなたがいてくれてよかった」と言われると、離れるのが怖くなる。
自分の予定よりも母親の感情を優先してしまう。
このように、自分の人生や感情を軸にできなくなり、常に「母親がどうか」に心が支配されます。
それは、ただの“優しさ”や“気遣い”のように映ることもあり、本人も周囲も、その深刻さに気づきにくいのです。
けれどその実態は、子どもの内側に深く根を張る「自己否定」と「感情の麻痺」。
その土台の上に、「母親に執着するしかない心の構造」が静かに作られていくのです。
2.離れられない心──執着の深まりと、孤立のはじまり
母親に否定され続けると、子どもは「本当の自分では愛されない」と感じはじめ、次第に母親の望む姿を演じるようになります。
そしてその姿で「よくやったね」と認められると、ほんの少しだけ安心する。
でもそれは、自分の“本音”や“自然な感情”を無視したうえでの安心です。
この不安定な安心感を繰り返すうちに、子どもは「母親からの承認なしには、自分は存在できない」と思うようになります。
ここから“執着”が、無意識のうちに強く深く育っていきます。
最初は、「母親に嫌われたくない」だった気持ちが、いつの間にか「母親のために頑張らなくては」「私が支えなければ」──
そんな責任や使命感にすり替わっていきます。
けれどこの感情は、幼い子どもが背負うにはあまりにも重く、苦しいもの。
そしてこの頃から、子どもは“外の世界”とのつながりを、自ら閉ざしていくようになります。
・友達と遊んでいても、母親の機嫌が気になって楽しめない。
・学校の出来事よりも、母親がどう感じるかが最優先になる。
・誰かに頼ったり助けを求めることが、「母親を裏切るように感じてしまう」。
こうして、子どもは母親以外の関係に不安を覚え、安心できる場所が“母親との関係の中だけ”になっていきます。
でもその関係の中では、本当の気持ちを話せない。
無理をして笑い、無理をして気を遣い、無理をして合わせる。
そうして心の奥に、“誰にも知られたくない自分”が積もっていきます。
母親との関係に依存しながらも、「本当は苦しい」「助けてほしい」「このままじゃ苦しい」とも言えない。
誰にも気づかれず、誰にも知られず、自分だけが、自分の中にある孤独に気づいている──
そんな状態が、日常になっていくのです。
だからこそ、この孤立は、外からは見えにくく、「いい子」「おとなしい子」「頑張り屋さん」と思われがち。
“母親との関係”にすべてを向けざるを得なかった子どもは、気づかないうちに、他の人とのつながりをあきらめることに。
そして、この心の“見えない孤立”が、次第に“生きづらさ”というかたちで、表に出始めていくのです。
3.執着が生んだ、きょうだいとの静かな分断
けれど、この“母親との関係”にすべてを向けざるを得なかった子どもは、気づかないうちに、他の人とのつながりをあきらめていくようになります。
同じ家で育ったきょうだいであっても──
例外ではありません。
きょうだいというのは、本来ならもっとも近くにいて、同じ空気を吸い、同じ景色を見ている存在です。
でも、“母親の気持ちを正しく読み取る”ことが最優先になると、その視線は常に「母」だけに向けられ、きょうだいを“仲間”ではなく、“ライバル”のように感じてしまう瞬間が生まれます。
たとえば──
・自分だけが叱られているように感じる
・きょうだいがほめられると、心がぎゅっと締めつけられる
・きょうだいの失敗に、なぜか自分が責められているような気がする
本当は、お互いに寄り添えたかもしれない。
でも、親の気分に合わせることに精一杯で、誰かと心を通わせる余裕が残されていなかったのです。
そうして、
「自分だけが、がんばらないといけない」
「きょうだいは、わかってくれない」
という思いが、じわじわ心に根を張り、同じ痛みを感じているきょうだいとの間にも、壁ができかねません。
。
この分断は、子どもたちの孤独をさらに深めていきます。
誰にも頼れない。分かってくれる人がいない。
“家族の中ですら、ひとりぼっち”という感覚が、静かに子どもの心を締めつけていきます。
次のお話では、この“きょうだいとの分断”がどのように生まれ、そしてそれが子どもたちの心にどんな影響を与えていくのか──
その繊細なプロセスを、具体的に解きほぐしていきたいと思います。
どうか、ひとつひとつの言葉の奥にある、気づいてもらえなかった痛みを、ここでそっと見つめてもらえたら嬉しいです。

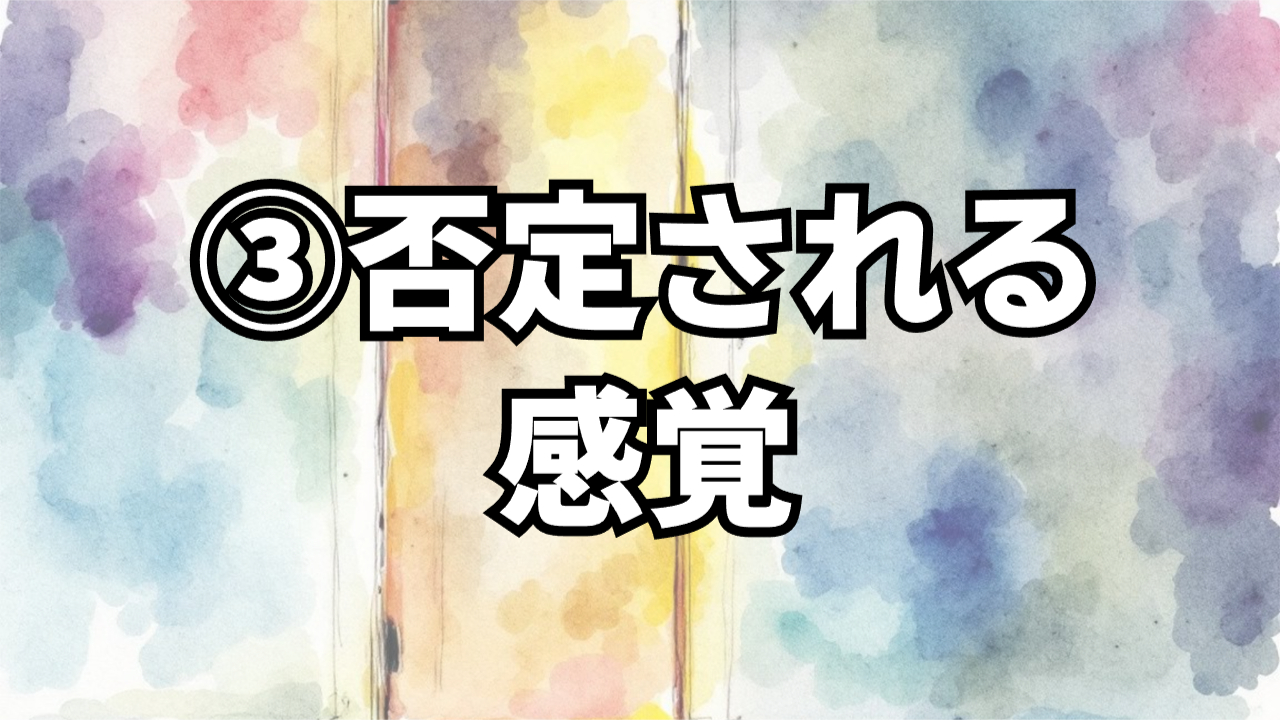
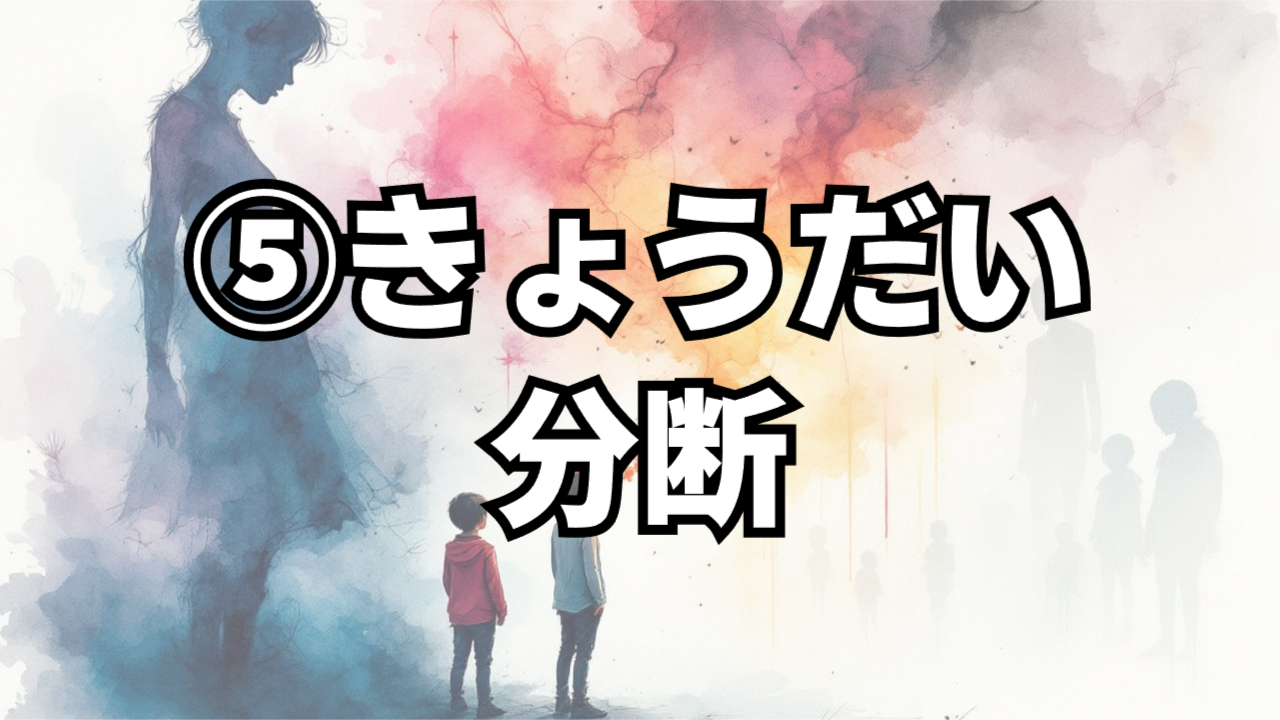
コメント