1.否定される感覚 ── 「聞きたくない」と耳を塞いだ、その奥にあるもの
たとえば、小さな子どもが一生懸命に母親の顔を見上げて、「これでいい?」と問いかける場面を想像してください。
それは、何気ないしぐさのようでいて、実は必死の確認作業なのです。
「母親の望む答えを出さなければ、また傷つけてしまうかも?」──
無意識にそう感じる子どもにとって、この問いかけは、ただの“質問”ではなく、“恐れ”と“願い”が入り混じった行為です。
けれど、母親の正解ははっきりと示されないことが多く、「それは違う」「そんなこと言う子じゃないと思ってた」などの言葉が返ってくると、子どもは自分の考えや感じたことそのものが“間違い”だったように受け取ります。
この積み重ねは、やがて「自分の思いを出すこと」そのものを諦めさせます。
“自分が感じること=否定される”という思い込みが、深く根づいてしまうのです。
そして、いつの間にか「自分の意思」がどこにあるのか、わからなくなっていきます。
何をしたくて、何が嫌で、どうしたいのか──
すべてが不明瞭になり、自分の存在自体に、自信が持てなくなっていく。
それが「自己肯定感を失う」という状態です。
ある子は、学校で友達の意見に合わせすぎてしまい、「自分がないね」と言われてショックを受けました。
でもその子にとっては、合わせることが生き残るための術だったのでしょう。
「間違えないように」「否定されないように」と、どこでも正解を探してしまう。
その習慣は、家庭の中で、母親の顔色を読み続けた日々から生まれたものかもしれません。
限界がきた子どもたちは、ついに「もう聞きたくない」と、心を閉ざします。
それは、わがままでも甘えでもありません。
心がすり減り、これ以上“否定”に耐えられないとき、自分を守るために「耳を塞ぐ」しかないのです。
不登校や言葉に出せない不調──
それらは「否定される感覚」が積み重なった末に起こる、“心の叫び”なのだと思います。
今、こうした感覚を持つ子どもたちが増えている背景には、無意識の「先読み」や「空気を読む」があたりまえになりすぎた社会や家庭の風土があります。
繊細に気を配りながら育った子どもたちは、お互いにも「読み合い」「探り合い」をし、ちょっとした違和感やズレに敏感になり、「否定された」と感じる体験をくり返すのです。
本当は誰も責めたくない。
けれど、その優しさゆえに、自分だけが傷を抱え続ける──
それが「否定される感覚」の、見えにくくも深い苦しみなのです。
2.心に残る “否定される感覚”──その始まりは、とても静かだった
否定されるという出来事は、必ずしも怒鳴られたり、拒絶されたりするような強い表現で現れるとは限りません。
それはときに、沈黙だったり、話を聞いてもらえなかったり、わずかな表情の変化やため息、あるいは、話をそらされた瞬間など──
とても静かなかたちで、子どもの心に入り込んできます。
たとえば、こんな場面があります。
「お母さん、今日はね、学校でね──」
と話しかけたときに
「あとにして」
と短く返される。その言葉が“ダメ”だったわけではないと頭ではわかっていても、
なぜか心の奥がキュッと痛くなる。
そんな小さな痛みを、子どもは日々、胸の中にため込んでいくのです。
あるいは──
自分が泣いたとき、困った顔をされる。
何かを頑張って伝えようとしたとき、「それは違う」とすぐに直される。そうしたやりとりが重なっていくと、
子どもは「何を言っても、何を感じても、間違ってるんだ」と思い始めます。
気づかないうちに、「自分のままでは認められない」「ありのままでは価値がない」と、心の奥に“否定される前提”が刷り込まれていくのです。
それは、とても孤独な体験です。
まだ言葉にならない感情を抱えながらも、「どうすれば否定されないか」を探す日々は、自分の本心よりも「正解らしきもの」を探すことばかりに意識が向きます。
でも、その正解はいつも変わります。
昨日は通じた言い方が、今日は通じない。
笑ってくれると思ったのに、なぜか怒られる。
その繰り返しのなかで、子どもはどんどん混乱し、
自分の感じていることに、自信を持てなくなっていくのです。
否定される感覚は、言葉よりも先に「空気」や「雰囲気」として伝わります。
だからこそ、「なんで自分がこんな気持ちになっているのか」が分からず、誰にも説明できないまま、ただ心に影のように残り続けるのです。
3.否定される感覚のその先に──「母親に執着していく子どもたち」
否定され続ける日々の中で、子どもたちの心は静かに、けれど確実に変わっていきます。
本当の思いを口にすれば、それが“否定”される。
感じたことをそのまま出すと、“間違っている”と言われる。
そんな日々が続くと、やがて子どもは「自分の感情よりも、母親の感情を優先する」ことを選ぶようになります。
自分の本音が否定されるくらいなら、いっそ最初から「感じない」「考えない」ふりをした方が安全だ──
そうして、子どもは自分の“感じる力”を少しずつ手放していきます。
でも、その代わりに必死で求め続けるものがあります。
それは、“母親の正解”です。
母親の期待や気分、言葉のニュアンスに細かく神経を張りめぐらせ、「今、機嫌はどうか」「これは怒られるか」「どうすれば喜ばれるか」そんな思考を何度も繰り返して、自分なりの“生き延びるルール”をつくっていきます。
このとき、子どもの視線はどんどん内向きになり、世界の中心が「母親」になっていきます。
それは愛情ではあるけれど、同時に“恐れ”でもあり、“依存”でもあり、やがて「母親に認められないと、自分は存在していない」と思い込むようになります。
たとえば、小さな成功があったとしても、「お母さんは、これを選んだら嫌かな」と考えて決められなくなる。
自分の感情ではなく、“母親にどう思われるか”が常に先にあるのです。
こうして、否定を恐れるあまり、子どもは母親の中に答えを探し続け、次第に「自分の生き方」そのものを母親に預けてしまいます。
母親の正解を求めて離れられなくなる。
時には、怒られても嫌われても、「つながっていたい」と願ってしまう。
それが、否定され続けた子どもが抱える、“執着”という形の痛みです。
それはわがままでも、甘えでもありません。
誰よりも大切だったはずの母親との関係の中で、“自分を失うほどに傷ついた”という、深い悲しみの表れなのだと思います。
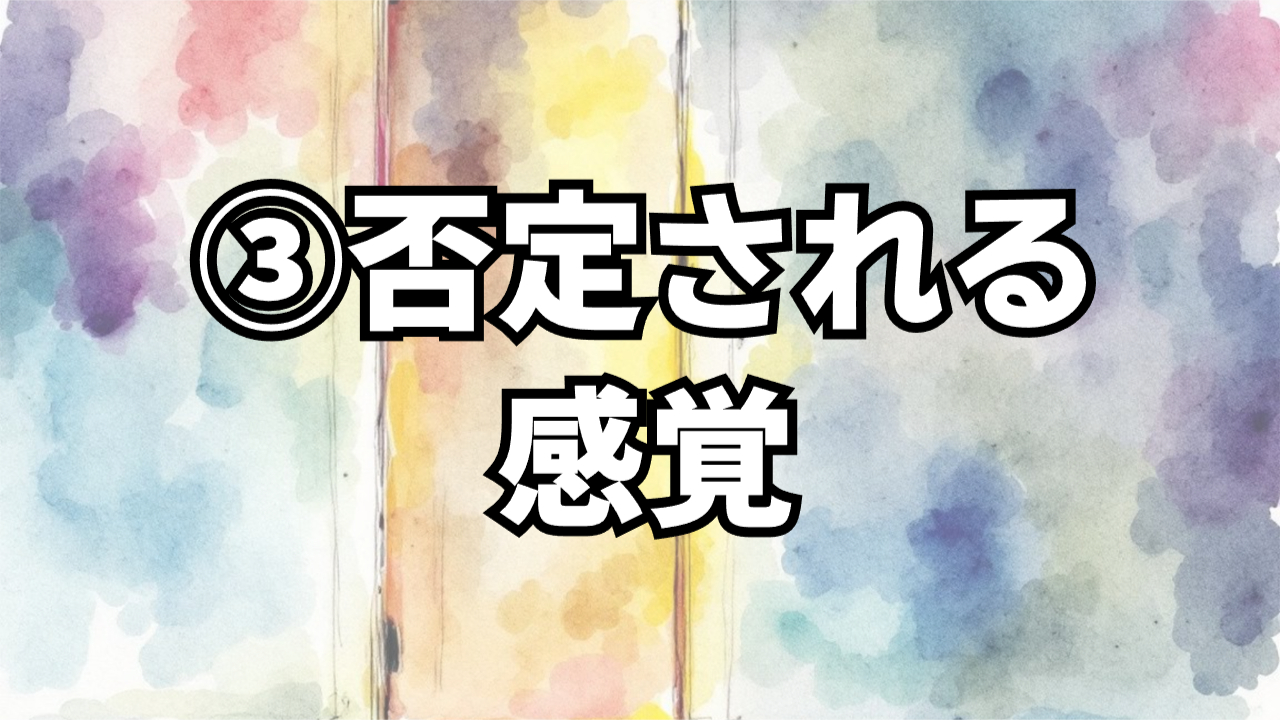


コメント