「兄弟姉妹の分断」がどのようにして起こり、どんな影響を与えていくのか──
1.兄弟姉妹を切り離す “静かな分断”
親との関係に巻き込まれるなかで、子どもたちは時に「兄弟姉妹」としての関係さえも奪われていきます。
それは大きな声で命じられたり、目に見える争いがあって壊れていくようなものではありません。
もっと静かに、もっと気づかれないかたちで、じわじわと心の距離を引き離されていくのです。
たとえば、母親が兄や姉にだけ期待をかけたり、逆に弟や妹だけを過度に守ろうとしたり──
その選別に正当な理由がないまま、「こっちはわかってくれない」「どうせあの子ばかり」
という感覚だけが、兄弟姉妹のあいだに溝を作ります。
また、「お父さんはダメな人」「あの子はちょっとおかしい」など、特定の家族を暗黙のうちに“はじく”空気が作られることも。
それは、「自分の身を守るため」に無意識でやってしまっていることでもあります。
誰かと親しくすることで、自分が責められたり、間違っていると思われるのが怖かったのかも?
そうやって築かれていく距離の正体が、“兄弟姉妹の分断”なのです。
本来なら、安心できるはずの家の中で
「なぜか一番近くにいるはずの兄弟に、心を許せない」
「同じ経験をしてきたはずなのに、どこかずっと遠い」
そんな感覚が、ずっと残ってしまう。
その感覚は、大人になってからも消えず、社会の中で誰かと深く関わろうとした時に現れます。
「どうせわかってもらえない」「信じても裏切られる」──
という思いとして、静かに顔を出すようになります。
兄弟姉妹との関係は、本来、人生の最初の“対人関係”であり、互いを通して学ぶはずだったコミュニケーションの土台です。
その土台が奪われたとき、私たちは“つながる力”そのものを奪われてしまうのです。
2.兄弟姉妹の分断が生む、深い孤立と生きづらさ
家族の中で、兄弟姉妹と心の距離が広がっていくと、それはただの「家族内の問題」では済まなくなります。
むしろその孤立は、次第に「社会全体」への不安と恐れに変わり、外の世界とどう向き合うかわからなくなっていくのです。
子どもたちは、兄弟姉妹との関係を築けなかったことが、他の人との関わりにも大きな影響を与えることに気づかず大人になっていきます。
他者との距離感が、無意識のうちに「家の中の空気」に影響され、「自分は人と上手く関われない」「どうしても孤立してしまう」と感じるようになっていきます。
この感覚は、大人になってからの生きづらさへと繋がります。
外の世界では、誰もが持っている“人間関係の基盤”──
他者との信頼関係を築くための土台が、育たなかったからです。
そのため、大人になった後でも、自分を他人に理解してもらうことができず、
「本当の自分を見せてはならない」「本当の気持ちは言えない」
という感覚が、常に頭の中に浮かび続けます。
その結果として、職場や友人関係、恋愛関係でも、不安や恐れが強くなり、結局は自分を守ろうと壁を作ってしまいます。
「どうしても他人を信じられない」「気持ちが素直に伝わらない」という感覚が、日々の生活の中で深まっていきます。
そして、子ども時代の家族の中での孤立感は、大人になってからも薄れずに、深い「孤独感」として心に残り続けることになります。
自分が孤立していることを気づいていない場合もありますが、その感覚が、どこかで自分を遠ざけ、世界とのつながりを弱めていきます。
この孤立感は、もはや家族の分断だけにとどまらず、社会全体に広がり、次第に自己肯定感の低下や、自己表現の困難さを引き起こします。
「こんな自分じゃダメだ」と思う一方で、「誰かに助けてもらいたい」と願っているのに、それを表現できないジレンマが、心の中で絡まり続けます。
3.孤立から共依存へ──「誰かに助けてもらいたい」と願う心
「こんな自分じゃダメだ」と感じながらも、「誰かに助けてもらいたい」と心のどこかで願っている。
この矛盾した思いが、やがて「共依存」という関係に繋がっていきます。
自己肯定感の低さと、他者に対する不安や恐れが入り混じった状態では、自分だけで世界と向き合うことが難しく、つい他者を頼ることも。しかし、その頼り方が、健全な支え合いとは言えないことが多いのです。
「誰かに助けてもらいたい」という思いが強まると、次第に自分の感情やニーズを他者に依存してしまいます。
相手が自分の期待に応えてくれることで、自分の存在価値を確認しようとするのです。
「相手へ過剰に依存してしまう」という状態は、やはり健全ではありません。
最初は自然に感じた頼りたくなる気持ちも、次第に「自分の感情や存在を他者に委ねる状態」に変わり、相手に対して過度な期待や、無意識の支配を求めるようになります。
このような関係が続くと、依存している相手が自分の心の中で絶対的な存在となり、それが「共依存」の状態を作り出し、自分の気持ちや判断を相手に任せることで、安心を得ようとします。
その一方、依存によって自分のアイデンティティがさらに曖昧になり、ますます自己肯定感が低下していくのです。
共依存の関係は、最初は互いに必要とされていると感じるかもしれませんが、次第にお互いの依存が重荷となり、負のスパイラルに陥っていきます。
相手が自分を満たしてくれなければ、「自分はダメだ」「相手に嫌われたらどうしよう」といった強い不安に苛まれます。その不安を解消するために、さらに相手に過剰な期待を抱くことも少なくありません。
結果として、共依存の関係は「愛情」ではなく、あくまで「依存」によって成り立ってしまい、お互いが不満や苛立ちを抱えながらも、なかなかその状態を抜け出せないことが増えます。
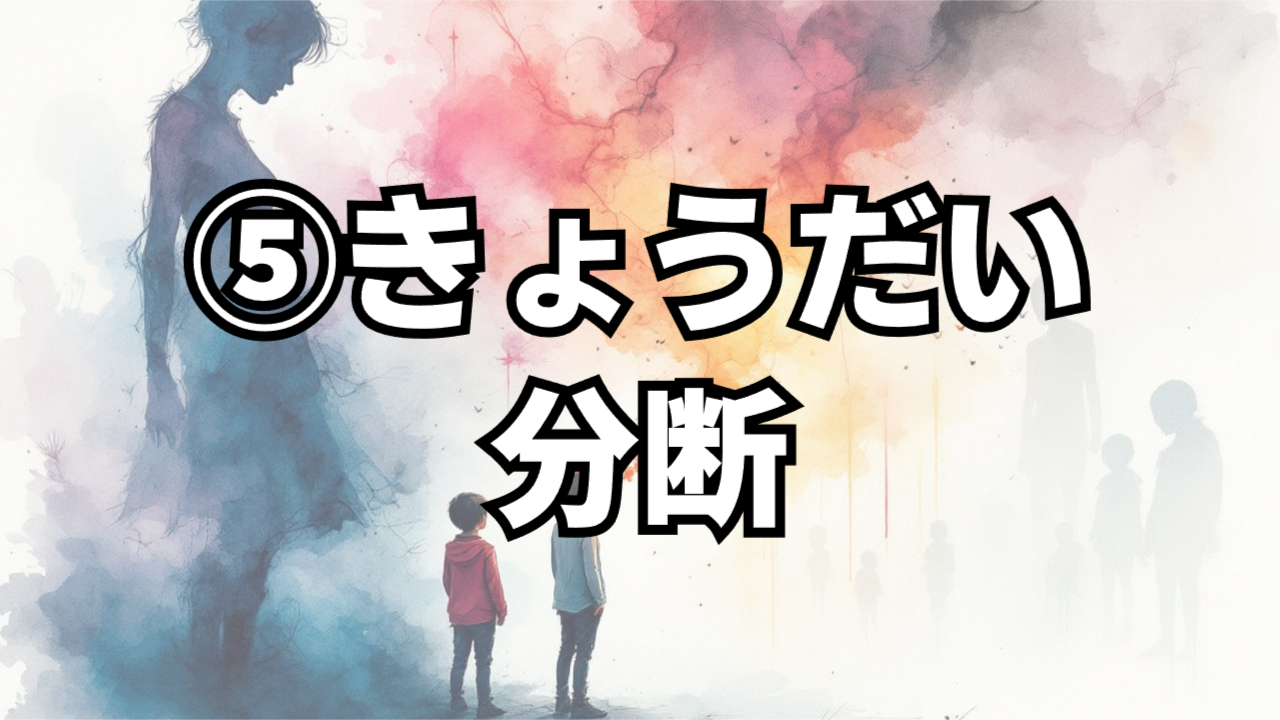


コメント